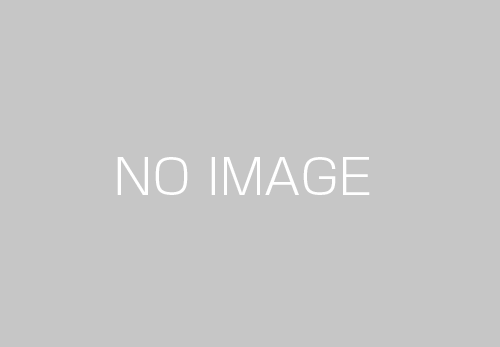1.カールマンオペレッタの笑い

オペレッタは、通常日本語では「喜歌劇」と訳されている。しかし、本来の意味は「小規模のオペラという意味で、「喜劇」に限定されてはいない。レハール後期の作品などには、ハッピーエンドにならないものもあるが、それは当時のウイーン国立歌劇場が、ヨハン・シュトラウスⅡ世の代表的作品を除いてオペレッタは採りあげなかった為、なんとか自作を上演して貰いたかったレハールが、意識してオペラ的作品を書いていたからと言われている。ただひとつオペラとの違いは、オペレッタの舞台上で人が死ぬ場面が私の知る範囲ではないということくらいだ。
かつて、1890年代にスッペ、シュトラウス、ミレッカーなど黄金時代を築いた大家たちが相次いで亡くなり、オペレッタが一時衰退した時期があった。
当時最高のオペレッタ俳優で、シュトラウスやカールマンなど多くの作品に主演したアレキサンダー・ジラルディも、演劇俳優に転身を決意して、ブルグ劇場の面接を受けた。そこではこんなやり取りがあったらしい。面接者「ジラルディさん、貴方は当劇場でどんな役をやりたいと思っていますか。」ジラルディ「何でもやるつもりです。ただ、死ぬ役だけは御免被りたい。」
オペレッタの笑いについて、ドイツの劇場監督で、レハールやカールマンの伝記を書いている シュテファン・フライは、その著作「エメリッヒ・カールマン伝」でウイーン・オペレッタの笑いの本質、特にカールマンの作品のそれについて述べている。
” 脚本家は、あらゆるジャンルで、たやすく機知と皮肉(Witz und Ironie)を提供できなければならない。だが、ユダヤ系の、多くのこの分野の頭脳がヒットラーの第三帝国のさなかに失われて久しい。
オペレッタ「メリーウイドウ」のテキストを書いたヴィクタ−・レオンは、次のように語っている。「オペレッタ・ファンは、”泣き笑い”を求めている。それは、我々ユダヤ人が2千年前のイェルサレムの破壊以来味わってきたものである。」
この定義はオペレッタ作曲家として、カールマンが表現してきたものも、全く例外ではない。特にカールマンの音楽からは、チャールダーシュの最高の幸せの中からも、涙を聞き取ることができる。また、死ぬほどの悲しみから天国的歓声まで急展開するのだ。”
このことは、代表作「チャールダーシュ女王」に接すればよくわかる。主人公達は、大きな希望実現の寸前に奈落の底に突き落とされ、そこから再び急展開してゆく。その泣いたり笑ったりをカールマンの音楽は的確に表現している。従って歌手・演奏者はその場面を忠実に再現していかなければならない。
笑いについても、シュテファン・フライが、必要なのは「機知と皮肉だ。」と言っている事は重要である。それはいわゆる「笑い」(Lachen)とは一線を画しているのである。
このことは、フォルクス・オパーの上演では、かなり厳格に守られているように思う。

2.オペレッタの起源とその笑い
オペレッタは19世紀中頃に、オッフェンバックが突然創造したかに思っている向きもあるかもしれないが、やはりそこに至る過程がある。
ヨーロッパのオペレッタは、16~17世紀にイタリアで発生した喜劇 コメディア・デアルテの影響を強く受けている。人気を得た一座はヨーロッパ中を回って興行した。
ウイーンへの影響は、主に二つの系統で入ってきた。一つは当時の文化国家であるフランスを経由したもので、モリエールの喜劇から、更にボーマルシェの戯曲はモーツアルトの「フィガロの結婚」へと繋がり、シカネーダー脚本の「魔笛」となる。
他方、直接ウイーンで興行した一座は、ウイーンの古典喜劇に強い影響を与えた。、ベルナルドン、シュトラニッキーを経て、ライムントのメルヘン劇、ネストロイの風刺劇にいたる。
これらの、ウイーン古典喜劇の多くは、演劇ではあるが、バックに小編成の楽団がつき、主演の俳優は数曲の主題歌を歌った。だから、ウイーンの主な俳優達は演技と共に歌の能力が高く、1860年にオッフェンバックが初めてウイーンを訪れて「天国と地獄」を上演して大当たりをとっても、スッペが直ちに「寄宿学校」で追随できたのは、そういうバックがあったことが大きい。
ここで重要なのは、コメディア・デアルテでは、伝統的に各登場人物の性格と役割がかなりはっきりと決められており、それがオペレッタの登場人物のそれに、相当部分が継承されていることである。
主な登場人物は、時代により名称等に変化は見られるものの大凡次のようなものである。1.二人の老人 − パンタローネ(欲張りで口やかましい商人・助言者、年甲斐もなく 恋をする。)、ドットーレ(似非学者・喜劇的風刺など)
2.二人のザンニ − ブリゲッラやアルレッキーノ 主として笑いを取る下僕役、
突っ込み役とぼけ役など対照的になることもある。
3.カピターノ − 大言壮語するが、実は気の小さい男など。
4.二組の恋人達 − 真面目な役・優雅で文学的素養が要求された。
5.小間使い − 明るく、活発。
これを「チャールダーシュの女王」の配役とくらべてみると、二組の恋人達、フェリ・バッチ、侯爵、支配人などの役に、明らかにその系譜が見て取れる。
また、これを見ると喜劇と言っても、笑いを取る役と、その対照的な役が巧く組み合って面白い劇を構成している。何でも笑わせれば良いわけではない。
3.日本に於けるウイーン・オペレッタ
日本に於けるオペレッタは、既に1870年代から、横浜や神戸の外人居留地などを中心に、バンドマン喜歌劇一座などにより紹介されていた。英国のサリヴァンやオッフェンバックなどのフランス系作品が多かった。レハールの「メリーウィドウ」、オスカー・シュトラウス「ワルツの夢」などは、初演(1905)数年後には上演されているが、英語上演だったと思われる。
これに対して、ヨハン・シュトラウスの作品の日本初演は、遙かに遅れて、1950年9月、藤原歌劇団の名古屋公演による「ジプシー男爵」が最初で、「こうもり」は1952年1月の東京歌劇団による仙台公演迄待たねばならなかった。まして、カールマンの「チーャルダーシュの女王」の初演は更に遅く、1982年、長門美保歌劇団によることとなる。
日本のファンが本物に接することが出来たのは、1979年以降のウイーン・フォルクスオパーの引っ越し公演が実現してからのことである。
こうして、私たちもウイーンの笑いに接することになったが、これを理解するのは大変難しい。
ウイーンで、ウイナーリード(ウイーンの伝統的民衆歌)の会に行くと、歌の間に
ウイナー・ムントアルトという一種の小話が語られることが多い。日本の落語の小話同様、最後に落ちがつく。そこで皆笑うが、我々外国人には理解できないことが多い。
また、ウイナーリードの歌詞には、表面的な意味以外に言葉に引っかけて、裏の意味があるものがあり、それは政治的風刺とか、セックスに関係するものだったりする。
こうした話芸はウィットに富んでいるものが多く、笑いを誘うといった感じであまり大笑いはしない。この特徴はウイーン・オペレッタにも生きている。
何が「笑い」となるかは、人種・民族により多様性がある。例えば、アメリカのショーの司会者のジョークなど聞くと、何がおかしいのかと考えてしまうこともある。
浅草オペラなどの、過去の日本のオペレッタでは、「ベアトリねえちゃん、まだねんねかい−−−」の歌詞のように、日本語訳のテキストでは、多少原作から離れても、日本的笑いを取り入れて、大衆化が図られることが多かった。
反面、それは原作から離れて、本来の作品の持つ美しさや優雅さなどを失い、クラシツク音楽の中では一段下に見られたり、オペレッタの矮小化に繋がったと思う。そして、現在でも若い歌手達が、オペレッタをそのように理解して、安易に笑いを取りたがる傾向が無しとしない。コミカー役(フロッシュ・ニェグシュなど)は自発的な笑いを取って良いが、笑いを決めるのは中々難しいものである。
多くの良いオペレッタの原テキストには、役割に従って忠実に演ずれば、必要な笑いが取れるように書かれていることを、もっと理解して欲しい。
スッペのオペレッタ「ボッカチオ」は早くから日本でも上演されていたが、従来の公演を見る限りでは、何か二流のコメディ・オペレッタのように思っていた。2008年のウイーン・フォルクスオパーの本格上演に接して、改めてこのオペレッタが、オペラに近い規模と,品格・楽しさを兼ね備えた佳作であることを知らされた。このギャップを埋めることは、大きな課題である。
この数年、佐藤智恵さんのムジカ・チェレステは、カールマンの作品に意欲的に挑戦して、日本のオペラ・グループとして初めてカールマンの3オペレッタ作品上演を達成した。
内容も再演ごとに充実してきている。しかし、なお課題も多い。今後望まれることの一つは、上記のカールマン・オペレッタの笑いの本質を充分理解した上で、いかに日本の愛好者にも合った笑いを創造することだと思う。